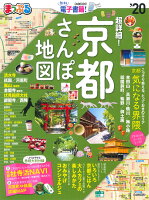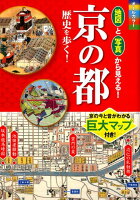嵯峨の虚空蔵さん
- 2019.10.12
- 右京区

渡月橋から眺める「嵐山」。春は桜、秋は紅葉が「嵐」のように散ることに由来します。
全長155mの渡月橋は欄干以外はコンクリート製です。
2013年9月16日、台風18号の時に流されそうになっている橋をテレビで見た姪から「おばちゃん、大丈夫」とラインが入りました。修学旅行でお馴染みの橋です。
渡月橋は承和年間(834〜848)に法輪寺を再建した僧・道昌(798〜875)によって架けられました。その後、幾度の破損や流出、再建を繰り返し、1606年に角倉了以(すみのくらりょうい 1554〜1614 61歳)によって現在地に架けられました(一説では今より100m下流にあったとされます)。
いよいよ目的地の「法輪寺」へ。

入り口は渡月橋を渡ってほぼ突き当りにありましたが、裏口?だったようです。歩いて10分程で、

狛犬ならぬ大きな口を開けた「狛虎?」が迎えてくれました。

こぢんまりした本堂です。法輪寺は奈良時代に第43代元明天皇(661〜721 61歳)の勅願により行基が創建。
829年に空海の弟子・道昌が虚空蔵菩薩を安置。874年に伽藍が整えられ、寺号を「葛井寺(かずのい)」から「法輪寺」に改められました。
本尊 虚空蔵菩薩(秘仏 こくうぞうぼさつ)
虚空蔵菩薩とは広大な宇宙のような無限の知恵と慈悲を持つ菩薩の意です。また、丑年と寅年の守り本尊です。
「十三詣り」でも有名です。数えで13歳になる男女が知恵と福徳を授かるために旧暦の3/13にお詣りします(現在は4/13の前後1ヶ月)。
お詣りが済んだあとの帰り道、渡月橋を渡り終えるまでに後ろを振り返ると知恵がお寺に帰ってしまうという言い伝えがあります。

本堂の右手に広い見晴らし台がありました。

東山が見えます。

子ども達が「だるまさんがころんだ」をしてました。

「電電宮」社です。電気や電子関係者から信仰されてます。


電電宮を降りた所に山門がありました。
-
前の記事

兄と弟…骨肉の争い。待賢門院 2019.10.11
-
次の記事

上尾にて 。 2019.10.15