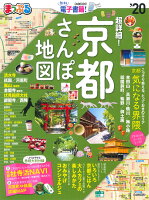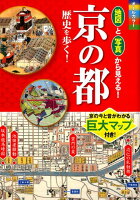松尾大社にて。
- 2020.01.10
- 未分類

自宅近くの堤防から四条をめざして。
五条手前の川岸の風景です。この先には渡月橋がありますが、ここら辺は荒れ放題です。
道も途切れたりして。特に五条から四条まではとんでもなく長い距離に感じました。
ボヤくのはこの辺にして。
この日は虹がかっていました。

松尾大社(正式にはまつのおたいしゃ)です。
鳥居の下には「脇勧請(わきかんじょう)」がありました。
脇勧請とは榊の小枝を束ねたもので12あり(閏年は13)、月々の農作物の出来ぐあいを占いました。
榊が完全に枯れると豊作、一部が枯れ残ると不作とか。

松尾大社のご祭神は
大山咋神(おおやまくいのかみ)
市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)
です。
大山咋神の祖父はスサノオノミコトです。
また、日吉大社(比叡山の麓)にも祀られており、「山の神さま」です。
松尾大社、日吉大社ともに巨大な磐座と古墳群が存在し、共通点が多いことが指摘されています。

時雨れる中、自転車で1時間あまり走って冷えたので…。

イケメンのお兄ちゃんの前を通ってトイレ休憩です。

「松尾大社」は701(大宝元年)、第42代文武天皇(683~707)の勅命で、秦忌寸都理(はたのいみきとり)が現在地に神殿を営み、山上の磐座の心霊を社殿に移したのが起源です。
秦氏は5世紀に渡来。秦の始皇帝の子孫と称していましたが、近年の研究では朝鮮・新羅の豪族とされています。

松尾の神さまの使いは亀です。
境内のいたる所に鎮座していました。

秦一族の特技のひとつに酒造があります。
室町時代末期以降、「日本第一酒造神」として仰がれています。

本殿の左手に「樽うらない」と

「相生の松」があります。
雌雄同じ幹からなり、約350年の天寿を全うしたとありました(それぞれ 昭和31、32年)。

焚き火に癒されました。が…。
大切なご本殿を撮り損ねていました。
本殿は1285(弘安8)焼失。
1394~再建、室町初期の1542年に大修理を施したと由緒書きにありました。
次回は昭和の名庭とご神水を紹介します。
-
前の記事

嵯峨野周辺…二尊院 2020.01.08
-
次の記事

松風苑と神像…松尾大社 2020.01.12