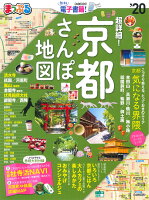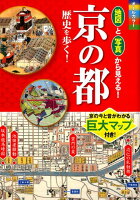六孫王神社その2…念願の源平咲きに出会いました。
- 2020.04.06
- 未分類
前回は染井吉野について書きましたが、付け加えまして…。
藤野寄命(ふじのよりなが 1848~1926 東京帝室博物館職員 )が上野公園の桜を調査していたところ、ヤマザクラとは異なる桜があることがわかり、その桜を「染井吉野(ソメイヨシノ)」と名付けたのが始まりです。
さて、「恋の架け橋」を渡るとかわった桜が。

「区民の誇り サトザクラ」とありました。

淡い緑色の花…。
サトザクラの品種のひとつ、
「御衣黄桜(ぎょいこうざくら)」
です。
咲き始めは淡い緑→徐々に黄色に変化→やがて花びらの中心部が赤く染まっていく
とありました。
咲き始めの花びらの緑が御衣(貴族の衣服)の色のひとつ萌黄色(もえぎいろ)に近いことに由来します。
江戸時代に京都・仁和寺で栽培されたのが始まりです。
本殿右手にも、

ひとつの木に白とピンクの花が咲いていました。

八重桜ではなく「源平ハナモモ」でしょうか?
1本の木に紅白の花が咲くことを”源平咲き”といいます。
平安時代の源平合戦の時、源氏が白旗、平氏が赤い旗を用いていたことから呼ばれています。
何故、花が変化するのか…。調べましたがわかりませんでした。

染井吉野よりも京都ばあばは紅枝垂れ桜が好きです。
一般的に花の先端が尖っているのが桃、桜はハートのように先割れしているとか。
また、枝と花の距離も見分けるポイントのようです。
桃は枝に沿うように咲き、桜は枝からやや離れて房状に咲きます。
-
前の記事

4/4→六孫王神社(ろくそんのうじんじゃ)の染井吉野(そめいよしの)が満開です。 2020.04.05
-
次の記事

六孫王神社その2…念願の源平咲きに出会いました。 2020.04.06