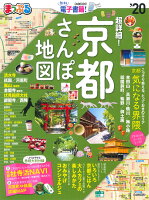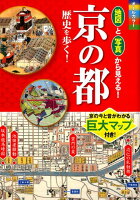東福寺その1 三門・本堂
- 2019.09.21
- 東山区
その後、幾多の変遷を経て、摂政・九条道家(1193〜1252 60歳)はこの地に高さ五丈(一丈は約3m)の釈迦像を安置する寺院を建立することを発願。
奈良の東大寺、興福寺のニ大寺から一字ずつとって「東福寺」としました。
1237(嘉禎2)年、19年の歳月を経て1255(建長7)年に七堂伽藍を完成。
しかし、焼失と再建を繰り返します。
1881(明治14)年、大火で仏殿、法堂、方丈が焼失しますが、幸いにも国宝の三門をはじめ、東司(便所)、浴室、禅堂などは焼け残りました。
まずは、国宝の三門へ。

とにかく大きい…です。1425(応永32)年、室町幕府第4代将軍・足利義持(1386〜1428 43歳)が再建し、現存する禅寺の三門としては日本最古です。
上層には宝冠釈迦如来坐像と十六羅漢(羅漢→最高の悟りを得た尊敬や施しを受けるのにふさわしい聖者。主に禅宗で尊ばれる)が安置され、明兆の極彩画が有名です。
1586(天正13)の天正大地震で傷み、秀吉が大修理した四隅の柱は「太閤柱」と呼ばれています。手前の池は「思遠池(しおんち」です。蓮の花は咲き終わっていました。

仏殿兼法堂の本堂です。
1881(明治14)年、仏殿と法堂が焼失したため、1917(大正6)年から10数年かけて1934(昭和9)年に完成。高さ25mもあります。
方丈庭園拝観受付で、「素敵な庭でした」と係りの方に声をかけると、「本堂の天井は見られましたか?」と言われたので本堂に戻り天井を見上げると可愛い龍が飛んでいました。

堂本印象(1891〜1975 85歳 京都市出身)が16日間で書き上げたといわれています。…またも、見逃す所でした。
本尊は釈迦三尊像です。お釈迦さまの両横には、
阿難(あなん。釈迦の十大弟子のひとり。出家後、常に釈迦の側にいて、教えを最もよく記憶しており、多聞第一と称されますが悟ったのは釈迦の滅後といわれます。120歳まで生きたとされる)
迦葉(かしょう。釈迦の十大弟子のひとり。釈迦の死後、教団を統率した)
が安置されていました。
明治14年の火災後に万寿寺から移されました。
-
前の記事

紅葉前の東福寺界隈その3 真面目に参拝を…光明院 2019.09.20
-
次の記事

東福寺その2 東司・禅堂 2019.09.22