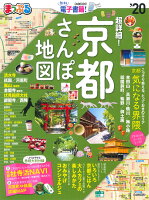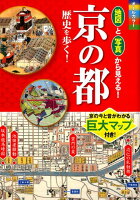京都御所周辺…護王神社
- 2019.12.25
- 未分類

烏丸丸太町を上ルと左手に見えてきます。
「護王神社(ごおうじんじゃ)」です。いのしし神社あるいは足腰を護る神さまとして参拝が絶えません。
創建 1866(明治19)年
主祭神
和気清麻呂公命(わけのきよまろこうのみこと 733〜799)
和気広虫姫命(わけのひろむしひめのみこと 730〜799)
清麻呂公は現在の岡山県和気町で生まれ、のち、奈良の都で朝廷に仕えました。
広虫姫は清麻呂公の姉で孤児救済事業で知られ、子育明神とも呼ばれます。
清麻呂公は京都・高尾山神護寺境内に祀られていましたが(祀られた起源は不明)、
1866(明治19)年、明治天皇の勅命で、華族・中院家邸宅跡地の京都御所蛤御門前(はまぐりごもんまえ)のこの地に社殿が造営、神護寺からご遷座されました。

境内にはいたる所に猪が置かれ、その数4000頭(奉納された縫いぐるみや木彫りなど)とも云われています。
手水舎にあるいのしし君の鼻はなでられすぎて光っていました。
鼻をなでると、「足腰がよくなる。」「再びここに戻って来れる。」「幸せが訪れる。」とか。
京都ばあばのお願い…「幸せにならなくてもよいですから、どうか不幸になりませんように。」とお祈りしました。

ここにもカワイイいいのしし君が…。

「座立亥串(くらたていぐし)」です。願い事を書いた札を1本の串にはさみ、本殿左の「願かけいのしし」の前に刺し願かけをします。
もう1本は家に持ち帰り神棚や棚の上など目線より高い位置にお祀りします。
また、本殿の右手には「足萎難儀回復の碑」があります。参拝者は足形の石の上に乗ったり、碑をさすったりして祈願します。
毎月21日の午後3時から「足腰祭」が行なわれています。

手水舎近くにある樹齢100年のカリンの木です。ゼンソク封じのご利益があります。
ここで和気清麻呂公について。
769(神護景雲3)、当時、法王となり権勢をふるっていた僧・弓削道鏡(ゆげのどうきょう 700?〜772)が「道鏡を天皇にせよ」と九州の宇佐八幡のご神託があったとして天皇になろうとします。
清麻呂は第48代称徳天皇(しょうとくてんのう 第46代 孝謙天皇と同一天皇 718〜770 女帝)に命じられて、ご神託の真偽を確かめるため宇佐八幡へ赴きます。
そして、宇佐八幡で清麻呂公は「天皇の後継者には必ず皇族のものを立てなさい。」とのご神託を受けます。
都に帰り、天皇に真のお告げを報告しますが、道鏡の怒りをかい、清麻呂公は足の腱を切られた上に姉の広虫とともに大隅国(おおすみこく 今の鹿児島)に流罪となります。
途中、皇室を守った宇佐八幡へ感謝するため立ち寄ることにしました。
一行が豊前国(福岡県東部)に至ると、どこからか300頭のいのししが現れ、清麻呂公の輿(こし のりもの)を囲み、道鏡が放った刺客たちから守りながら十里(40km)の道のりを案内します。
清麻呂公が参拝を終えるといのしし達は立ち去り、足萎えも不思議と治り、歩けるようになりました。
この故事により護王神社は足腰を守護する神社となりました。
770年、称徳天皇が崩御されると道鏡は関東へ下向。
清麻呂公は都に戻され、朝廷内では桓武天皇の信頼も厚く、長岡京から山背国葛野郡に遷都を進言。793年、造営大夫に任じられ、794年に平安京遷都となります。

京都で伊勢神宮遥拝所がある神社も珍しいのでは?
京都御所にも向かっています。
※1890(明治23)〜1939(昭和14)に発行されていた10円紙幣には和気清麻呂公が描かれていました。
-
前の記事

京都御所周辺…梨木神社 2019.12.24
-
次の記事

アパホテルの東に歴史あり…その1 道祖神社 2019.12.27