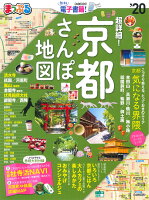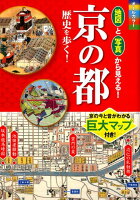首途八幡宮(かどではちまんぐう もと内野八幡宮)
- 2020.03.23
- 未分類

この地は源氏物語に登場する桃園親王(第56代清和天皇の第六皇子・貞純親王)の旧跡でした。
昔は境内も広く、池や築山をめぐらし、桃の木が咲く頃に桃花祭が執り行われました。
その後、奥羽の商人・伝説的人物の金売吉次(橘次 かねうりきちじ)の屋敷があったとされます。

参道には、

「源義経奥州首途之地」の石碑が建っていました。
1174(承安4)年の3月3日未明、牛若丸(のちの源義経)は鞍馬山を抜け出し、この地で吉次と会い、「内野八幡宮」に道中安全と武勇の上達を祈願して、奥州平泉の藤原秀衡(ふじわらのひでひら1122?〜1187)のもとへ首途(旅立ち)したと云われます。

以降、「内野八幡宮」から「首途(かどで)八幡宮」と呼ばれるようになりました。
義経、16歳の旅立ちです。

左手の石の鳥居をくぐり、

わずかばかりの石段を登ると本殿に到着。

本殿前の梅です。
【 ご祭神】
誉田別尊(ほんだわけのみこと 第15代応神天皇)
比咩大神(ひめのおおかみ)
息長帯姫命(おきながたらしひめのみこ と 応神天皇の母)
大分県・宇佐八幡宮より神霊を勧請し祀られました。
度々の災害でことごとく失われましたが昭和40年代に西陣の人たちを中心に再興されました。
 ご利益は…旅行安全や交通安全、厄除、勝運、小児の虫封じ、安産です。
ご利益は…旅行安全や交通安全、厄除、勝運、小児の虫封じ、安産です。 「首途天満宮」の北隣には、
「首途天満宮」の北隣には、 西陣の名水のひとつ「桜井」の井戸があったと云われる「桜井公園」がありました。ちょっとした日本庭園です。
西陣の名水のひとつ「桜井」の井戸があったと云われる「桜井公園」がありました。ちょっとした日本庭園です。
-
前の記事

堀川今出川…京都市考古資料館そして柚餅(ゆうもち) 2020.03.22
-
次の記事

報恩寺(通称・鳴虎) 2020.03.25