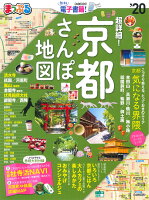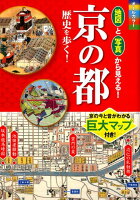大覚寺その2…嵯峨菊と名古曽の滝
- 2019.11.29
- 未分類

「大覚寺」へはこの門から入ります。

以前から見たかった嵯峨菊です。
嵯峨菊は大沢池の菊ケ島に自生していた野菊を長年に渡って洗練。
一鉢3本、高さ1、8〜2mに仕立て、葉は上部から淡緑→緑→黄色→茶色と春夏秋冬を表現しています(色の変化は、はっきりとはわかりませんでした。)

上から三輪(天を表すとか)、中部は五輪(人)、下部は七輪(地)の花が咲いていました。
花の色は白が「御所の雪」、黄が「御所の秋」、朱が「御所錦」、ピンクが「御所の春」と命名されています。
毎年11月の「嵯峨菊展」では約700鉢が寺内に展示されます。

五大堂の東面にある「観月台」の下には小川が流れていました。右手には「大沢池」が広がります。

「大沢池」は周囲1kmの日本最古の人工池です。
中国の洞庭湖(どうていこ)を模して造られたと云われます。
旧暦の8/15にあわせて行われる「観月の夕べ」は船から水面に写る月をめでるとされます。

「名古曽滝(なこそのたき)」跡です。
大沢池の北東100mの所にあり、嵯峨院滝殿の石組跡です。
藤原公任(ふじわらのきんとう 966〜1041 76歳)の句に
「滝の音は絶えて久しくなりぬれど 名こそ流れてなお聞こえけれ」 (小倉百人一首55番)
訳…滝の流れる水音は聞こえなくなってからもうずいぶんになるけれども、その名声だけは流れ伝わって、今でも人々の口から聞こえていることだよ。
公任は平安時代中期の公卿で漢詩や和歌、管弦に秀でてました。
平成6年からの発掘調査では、遣水(やりみず)が発見されました。
※遣水(やりみず)…寝殿造の庭園などで、外から水を引き入れてつくった流れ

時代劇のロケが行われていました。大覚寺は太秦撮影所に近い事もあり、幾多の時代劇の舞台となりました。

不動明王「災落とし絵馬」です。

愛猫用、愛犬用とカラフルなお守りが並んでいました。

お約束の甘味は…左は俵屋吉富の京まんじゅう栗、右はバイカルの月水鏡です。
-
前の記事

大覚寺その1…写経の寺 2019.11.27
-
次の記事

お火焚まんじゅうと線香そして山茶花。 2019.11.30