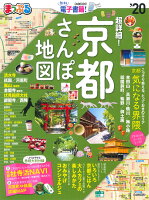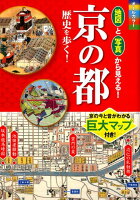嵐山の名所…天龍寺
- 2019.12.29
- 未分類

右手の庫裏(くり 台所兼寺務所)から入ります。
本堂参拝券300円と庭園参拝券500円の計800円払います。

まずは禅宗の開祖・達磨さまが迎えてくれました。この達磨図は元天龍寺管長・平田精耕(1924〜2008)氏作です。
大方丈は6部屋からなり、物外道人(もつがいどうじん)作の襖に描かれた雲龍図(レプリカです)も迫力があります。

大方丈縁側より眺めた「曹源池(そうげんち)庭園」です。国の史跡・特別名勝第1号です。
特別名勝は文部科学大臣が文化財保護法に基づき指定されたもとで、2019年7月現在36件しかありません(うち23ヶ所が庭園)
開山の夢窓疎石(国師 1275〜1351 臨済宗の禅僧)が作庭。
「王朝文化の優美さと禅文化が溶けあった庭」です。
日本最古の石橋や釈迦三尊石、龍門の瀧等の石組の数々…灰緑の池の色に目を奪われました。
曹源池は「曹源一滴」の禅語が由来です。
一滴の水はあらゆる物の根源である…の意です。
夢窓国師が池の泥をあげたとき、池中から「曹源一滴」と記した石碑が現れたところから名付けられたと云われます。

小方丈(書院)から写経場に通じる廊下からみたお庭です。
小川が流れており、何故か心安まりました。
天龍寺は
1339(暦応2)年、奈良・吉野で崩御された第96代および南朝初代天皇である
後醍醐天皇(1288〜1339)の菩提を弔うため、足利尊氏(1305〜1358)が夢窓国師を開山として創建されました。
この地は第52代嵯峨天皇の皇后・橘嘉智子(たちばなのかちこ 786〜850)が開いた檀林寺があった場所です。
檀林寺は京都で最初に禅を講じた寺で、壮大な寺院でしたが、皇后の没後に衰退しました。
その後、後嵯峨上皇(ごさがじょうこう 第88代天皇 1220〜1272)の仙洞御所(せんとうごしょ 譲位した天皇の御所 仙洞とは本来、仙人の住処をさしますす)・亀山殿が営まれました。
後醍醐天皇はこの地で幼少期を過ごしたとされます。
当時、室町幕府には南朝との戦いで財政的に逼迫しており、尊氏らの寄進では足りず、夢窓国師は、資金調達のために元との貿易を進言します。
1342年、室町幕府公認の下に出航。
その「天龍寺船」は莫大な富をもたらし、1343(康永2)年には七堂伽藍が整いました。
天龍寺は創建以来、8回もの火災にあっています。幕末には長州藩の陣営となり幕府軍の攻撃をうけて焼失。
建物のほとんどは明治時代の再建です。
1994(平成6)年に世界遺産に認定登録されたのは「曹源池」によるものです。
天龍寺の法堂天井の1997年に描かれた「八方睨みの雲龍図(加山又造作 1927〜2004)」も有名ですが、通常は土日祝日または特別公開時しか公開されていません。
なお、境内には龍門亭(篩月)があり、精進料理を食べることができます。
-
前の記事

天龍寺参道にて 2019.12.29
-
次の記事

竹の径…そして、大河内山荘へ。 2019.12.31